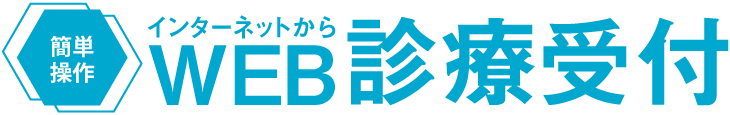腰椎分離症は、特に10代に好発する疲労骨折の1つとされており、腰椎後方の椎弓部分の連続性が失われることで様々な症状を発症します。初発症状は腰痛ですが、進行すると下肢の坐骨神経痛やしびれを生じることがあり、X線やCT・MRIを用いた早期診断が重要です。治療法としては、発症早期であればコルセットを用いた徹底的な安静が重要です。リハビリテーションやストレッチは、腰椎分離症の症状緩和を目的とした運動療法の一つです。改善が乏しい場合には、手術療法も考慮されます。
腰椎分離症とは
腰椎分離症は、腰椎の後方に位置する椎弓が骨折を起こし、それによって連続性が失われて分離してしまう疾患です。この状態では腰椎の後方部分の支持性が失われるため、徐々に椎体が前方にずれて神経を圧迫することがあり、腰椎分離すべり症へと進行する可能性があります。10代にスポーツや労働を繰り返すことによって起こる疲労骨折の一種と考えられています。腰椎分離症は、早期診断と適切な治療は、症状の進行を抑制し、良好な経過につながる可能性があります。
症状と原因
腰椎分離症は、腰椎の後方に位置する椎弓部分の連続性が失われてしまう疾患です。先天性の患者さんなど、遺伝的な要素で発症する方もいますが、大多数の症例の原因は青少年期にスポーツや労働によって腰椎に過度の負担がかかることによって発症する疲労骨折の一種と考えられています。腰痛が主な症状となり、自然軽快と再発を繰り返すことが多いです。腰椎分離症では腰椎の後方部分の支持性が失われるため、徐々に椎体が前方にずれて神経を圧迫されることがあり、下肢の痛み、しびれ、筋力低下を生じることがあります(腰椎分離すべり症)。
診断方法
腰椎分離症の診断は、まず患者さんの症状を詳細に確認することから始まります。病歴の把握に続いて、身体的診察を実施し、腰部の可動域や痛みの部位を確認します。画像診断は診断の要であり、X線検査によって骨の異常や分離の有無を確認します。ただし、分離症の初期段階では、X線検査で診断が難しい場合もあり、早期診断にはMRI検査が有効な場合があります。また、分離部の骨の状態を詳細に評価するためにはCTも重要です。これらの画像診断は、骨や軟部組織の状態を評価し、他疾患との鑑別を可能にします。早期診断は症状の進行を防ぐために欠かせず、適切な治療方針の決定に繋がります。MRIやCTなどの画像検査が必要な場合は、患者様のご希望を伺いながら、適切な医療機関への紹介も行います。
腰椎分離症の治療方法
腰椎分離症の治療方法は発症時期に応じて異なる対応が取られます。発症から間もない場合には、最低6か月間のスポーツ禁止やコルセットの着用など、保存療法を行うことで分離部の骨癒合が期待できることがあります。しかし、急性期を過ぎてしまっている場合には、すでに分離部の骨癒合が期待できないため、疼痛がコントロールできるのであれば必ずしもスポーツや仕事を禁止する必要はありません。鎮痛薬を使用したり、理学療法を行うことで症状の軽減を図ります。理学療法では、筋力を強化し、柔軟性を向上させるための特定のエクササイズやストレッチが行われます。
また、治療の一環として、日常生活の中での姿勢の改善や、腰に負担をかけない動作の指導が行われることもあります。これにより、症状の悪化を防ぎ、再発を予防することが可能です。患者様それぞれのライフスタイルに応じた個別のケアプランを策定することが、長期的な健康維持にとって重要です。治療の進行状況を定期的に評価し、必要に応じて治療計画を調整することも、効果的な管理に寄与します。
一方、保存療法が効果を示さない場合や、腰椎分離すべり症へと進展して神経症状が出現した場合には、手術が検討されます。一般的には腰椎椎体間固定術が選択されますが、年少の方の場合には症例を選んで分離部固定術が選択されることもあります。これらの手術は、腰椎の安定性を高め、神経への圧迫を軽減することを目的としていますが、リスクも伴います。手術の適応については、医師と十分に相談することが重要です。
当院では、手術が必要な場合には、同一法人の調布くびと腰の整形外科クリニック(https://sekitsui.clinic/surgery/)をご紹介いたします。
リハビリテーションとストレッチ方法
腰椎分離症に対するリハビリテーションやストレッチングは、痛みの軽減や機能回復の補助となる可能性があります。リハビリテーションでは、背骨や腹部の筋肉を強化するエクササイズを行い、腰部の安定化を図ります。また、ストレッチングは、柔軟性の向上や筋肉の緊張緩和に役立つと考えられています。運動は徐々に負荷を増やしながら行い、痛みが悪化する場合は即座に中止し、医師に相談してください。症状を確認しながら、継続的なリハビリテーションとストレッチングは日常生活の質を向上させる鍵となります。個々の進行状況に応じて、無理なく続けることが大切です。