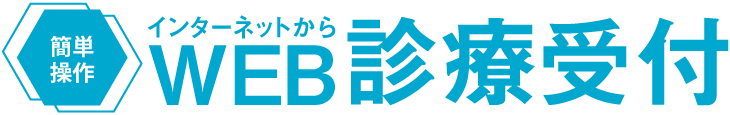頚椎症性脊髄症とは
頚椎症性脊髄症(けいついしょうせいせきずいしょう)は、頚椎の変性により脊髄が圧迫されて生じる疾患です。加齢や姿勢の変化、外傷などが原因で首の骨が変形し、脊髄や神経根に影響を及ぼします。特に中高年に多く見られ、放置すると神経症状が進行することがあります。
脊髄の圧迫により、しびれや筋力低下など多様な症状が現れ、日常生活に支障をきたすこともあります。早期発見とリハビリテーションを含む適切な治療を受けることで、症状の進行を抑え、生活の質を保つことを目指します。治療の効果には個人差がありますので、医師にご相談ください。
頚椎症性脊髄症の原因
頚椎症性脊髄症は、頚椎の変性により脊髄が圧迫されることで発症します。年齢とともに椎間板や関節が劣化し、骨棘(こつきょく)が形成されたり、靱帯が肥厚して神経を圧迫することで神経症状が現れます。
加齢に伴いリスクは高まりますが、若い方でも発症することがあります。早期に発見し適切な治療を行うことで、症状の進行を抑えることを目指します。定期的な健康診断や姿勢のケアも大切です。
頚椎症性脊髄症の症状
初期には、手や指先のしびれや違和感など軽度の症状が出ますが、見過ごされることも少なくありません。首や肩の痛み、こわばりを感じることもあり、日常生活の動作に影響を及ぼす場合もあります。
進行すると、手足のしびれや筋力低下により、ボタンを留める・お箸を使う・字を書くといった細かい動作が難しくなります。歩行時のふらつきや階段の昇降困難などバランス障害が見られることもあります。重度になると、四肢の筋力低下や運動麻痺、排尿・排便のコントロールが難しくなる膀胱直腸障害を伴うこともあります。
症状はゆっくり進行することが多いですが、転倒などをきっかけに急激に悪化することもあります。そのため、早期に受診し、医師と相談しながら治療方針を決定することが重要です。
頚椎症性脊髄症の検査方法
診察ではまず症状や神経学的な所見を確認します。その後、画像検査としてX線、MRI、CTなどが行われます。
- X線検査:骨の変形や狭窄の有無を確認します。
- MRI検査:脊髄や神経の圧迫状態を詳細に確認できます。
- CT検査:骨構造をより詳しく確認でき、MRIでは見えにくい部分を補足します。
- 神経生理検査(神経伝導速度検査・筋電図):他の神経疾患との鑑別に有用です。
これらを総合的に判断し、最適な治療方針を検討します。MRIやCTの実施は医師が必要に応じて判断し、専門機関をご紹介する場合もあります。
頚椎症性脊髄症の治療方法
治療は大きく「保存療法」と「手術療法」に分けられます。
頚椎症性脊髄症は進行性の傾向があるため、症状の程度や進行具合に応じて治療法を選択します。
保存療法
軽症例では、姿勢や生活習慣の改善、運動療法、薬物療法などが行われます。
薬物療法では、神経の健康維持を目的としたビタミン製剤や、痛みの緩和を目的とする消炎鎮痛薬などが用いられる場合があります。理学療法では、筋力維持や柔軟性を高める運動を理学療法士の指導のもとで行います。
手術療法
症状が進行している場合や日常生活に支障をきたす場合には、手術を検討します。手術には椎弓形成術や前方固定術などがあり、病態に応じて選択されます。手術後はリハビリテーションを行い、機能回復を目指します。
手術による改善には個人差がありますので、医師と相談しながら方針を決めていきます。
当院では、患者様の症状や生活背景を踏まえ、丁寧な説明と情報提供を行いながら治療を進めています。手術が必要な場合には、同一法人の調布くびと腰の整形外科クリニックと連携し、専門医による診療体制を整えています。